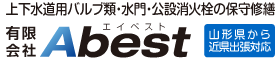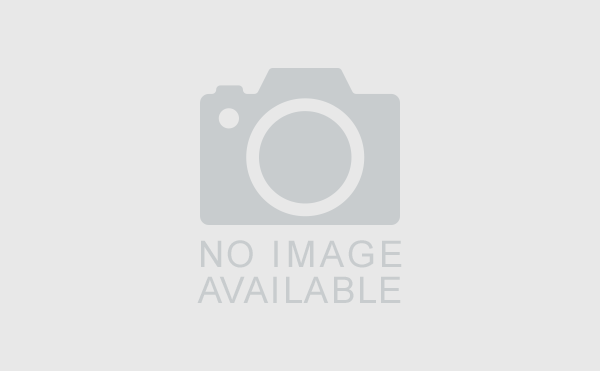モマタ地上式消火栓のオーバーホール
茂又鐵工所製の地上式消火栓の整備事例です。五角形の操作キャップが特徴です。メーカー名は丸万茂又や茂又鉄工所など、いくつかバリエーションがあるようですが、詳細は不明です。

操作キャップ周辺から漏水するため、地上からできるオーバーホールを実施しました。該当部分のパッキンの硬化と錆が原因ですので、部分的に修理が行えそうな印象を持たれるかと思いますが、一部のゴムだけが硬化したり、著しく錆びることはありませんので、すべてのパッキンは同じように硬化しており、腐食が進んでいると考えるのが自然です。

地上から分解できる部品をすべて分解します。放水口も分解できますが、ねじ山が損傷して再使用不能となるケースが多いため、必要がなければ分解しない方針です。分解と破壊は紙一重の作業です。

やはり弁軸の先端が腐食で欠損していました。この部分が欠損すると開閉が不安定になり、更に腐食が進めば開閉不能となるところでした。

弁軸を作製して交換してもよいのですが、他に損傷がないことから、部分修理をして再使用することにしました。溶接で欠損部分を肉盛りします。

欠損部を復元しました。グラインダーとヤスリを使った手作業で形成します。錆びた部品を工作機械で加工するのは色々と問題があって困難なためです。

部品を清掃しました。写真ではわからないことですが、溝や穴、パッキンの当たり面を徹底的に綺麗にしています。スムーズに作動するかや、きちんと密封するかは、これらがきちんと清掃されているかが非常に重要となります。

部品を塗装しました。塗料はエポキシ塗料を使用しています。強固な塗膜が形成されるのでスレや傷に強く、機械部品の補修塗装には最適です。

隠れてしまう部分も防錆塗料を施します。薄く塗る必要があるため、この部分は赤錆スプレーを使用しています。

消耗品はすべて交換します。廃盤機種なので、パッキンや消耗性の専用部品なども作製して対応します。本体や直管など大型の部品は作製できませんが、弁軸や軸受、安全座金、めねじや放水口などの主要な部品は、ほぼ作製可能です。

圧力検査を行って漏水がないかを確認します。この機種は、弁軸に腐食による表面の荒れ(孔食)が少しでもあると、本体上部から漏水します。このケースでは研磨で再利用することができましたが、故障率があまりに高いので、現在は弁軸交換を前提としています。

組み立てが完了しました。この段階になると通りがかる人に「新品に替えたの?」と声をかけられることがよくあります。「いいえ、修理です」と胸を張って答えるのが何よりの楽しみです。